社会保険労務士(社労士)は、社会保険労務士法という法律に基づく国家資格だ。この社労士になるには、社労士試験の合格等により資格を有することが必要になってくる。
僕は何度も何度もこの試験を受け、そして落ち続けた。落ちることが毎年の恒例になっていたある日、届いた郵便物を開けたら合格証書が入っていた。信じられなかった。
今でも合格したのが信じられないぐらいだ。
この試験の合格率はとても低い。
第53回試験(令和3年度)が7.9%、第52回試験(令和2年度)が6.4%、第51回試験(令和元年度)6.6%、第50回試験(平成30年)6.3%、第49回試験(平成29年)6.8%、第48回試験(平成28年)4.4%、第47回試験(平成27年)はなんと2.6%だ。
つまり受験して落ちる人が圧倒的に多い試験ということになる。
何度も落ち続けた知識?を整理して、社労士試験合格の勉強法を披露したいと思う。
社労士試験の合格するには
社労士試験で合格を目指すには、合格基準点を知りそれを満たす勉強をする必要がある。
そのためには、どのような試験か調べておく必要がある。
試験科目、方法と配点
試験科目は8科目である。
社会保険労務士試験の試験科目と配点
| 試験科目 | 選択式 計8科目 (配点) | 択一式 計7科目 (配点) |
| 労働基準法及び労働安全衛生法 | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 労働者災害補償保険法 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) | 1問(5点) | 10問(10点) (徴収法3問含む) |
| 雇用保険法 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) | 1問(5点) | 10問(10点) (徴収法3問含む) |
| 労務管理その他の労働に関する一般常識 | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 社会保険に関する一般常識 | 1問(5点) | |
| 健康保険法 | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 厚生年金保険法 | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 国民年金法 | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 合 計 | 8問(40点) | 70問(70点) |
選択式 10:30~11:50(80分)
選択式・・・1問につき空欄が5つ、空欄に選択肢の中から1つ選択
択一式 13:20~16:50(210分)
択一式・・・5つの肢の中から、1つ選択(正しいもの、又は誤っているもの)
社労士試験の合格基準点

合格基準点は、合格発表日に公表されるが、選択式試験及び択一式試験のそれぞれの総得点を満たし、かつ各科目とも最低必要な得点を満たす必要あるのだ。
つまり、
である。
社労士試験の年度ごとの合格基準
実際の年度ごとの合格基準はどうなのか平成18年度から表にすると下記の通りになる。
社労士試験の合格基準推移
| 年度 | 試験 | 総得点 | 各科目 |
| 合格率 | |||
| 令和3年度 (第53回) | 選択式 | 24点以上 | 労務管理その他の労働に関する一般常識 1点以上 国民年金法 2点以上 その他 3点以上 |
| 7.9% | 択一式 | 45点以上 | 各科目 4点以上 |
| 令和2年度 (第52回) | 選択式 | 25点以上 | 労務管理その他の労働に関する一般常識 2点以上 社会保険に関する一般常識 2点以上 健康保険法 2点以上 その他 3点以上 |
| 6.4% | 択一式 | 44点以上 | 各科目 4点以上 |
| 令和元年度 (第51回) | 選択式 | 26点以上 | 社会保険に関する一般常識 2点以上 |
| 6.6% | 択一式 | 43点以上 | 各科目 4点以上 |
| 平成30年度 (第50回) | 選択式 | 23点以上 | 社会保険に関する一般常識 2点以上 国民年金法 2点以上 その他 3点以上 |
| 6.3% | 択一式 | 45点以上 | 各科目 4点以上 |
| 平成29年度 (第49回) | 選択式 | 24点以上 | 雇用保険法 2点以上 健康保険法 2点以上 その他 3点以上 |
| 6.8% | 択一式 | 45点以上 | 厚生年金法 3点以上 その他 4点以上 |
| 平成28年度 (第48回) | 選択式 | 23点以上 | 労務管理その他の労働に関する 一般常識 2点以上 健康保険法 2点以上 その他 3点以上 |
| 4.4% | 択一式 | 42点以上 | 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 3点以上 厚生年金保険法 3点以上 国民年金法 3点以上 その他 4点以上 |
| 平成27年度 (第47回) | 選択式 | 21点以上 | 労務管理その他の労働に関する 一般常識 2点以上 社会保険に関する一般常識 2点以上 健康保険法 2点以上 厚生年金保険法 2点以上 その他 3点以上 |
| 2.6% | 択一式 | 45点以上 | 各科目 4点以上 |
| 平成26年度 (第46回) | 選択式 | 26点以上 | 雇用保険法 2点以上 健康保険法 2点以上 その他 3点以上 |
| 9.3% | 択一式 | 45点以上 | 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 3点以上 その他 4点以上 |
| 平成25年度 (第45回) | 選択式 | 21点以上 | 社会保険に関する一般常識 1点以上 労働者災害補償保険法 2点以上 雇用保険法 2点以上 健康保険法 2点以上 その他 3点以上 |
| 5.4% | 択一式 | 46点以上 | 各科目 4点以上 |
| 平成24年度 (第44回) | 選択式 | 26点以上 | 厚生年金保険法 2点以上 その他 3点以上 |
| 7.0% | 択一式 | 46点以上 | 各科目 4点以上 |
| 平成23年度 (第43回) | 選択式 | 23点以上 | 労働基準法及び労働安全衛生法 2点以上 労働者災害補償保険法 2点以上 社会保険に関する一般常識 2点以上 厚生年金保険法 2点以上 国民年金法 2点以上 その他 3点以上 |
| 7.2% | 択一式 | 46点以上 | 各科目 4点以上 |
| 平成22年度 (第42回) | 選択式 | 23点以上 | 社会保険に関する一般常識 2点以上 健康保険法 2点以上 厚生年金保険法 2点以上 国民年金法 1点以上 その他 3点以上 |
| 8.6% | 択一式 | 48点以上 | 各科目 4点以上 |
| 平成21年度 (第41回) | 選択式 | 25点以上 | 労働基準法及び労働安全衛生法 2点以上 労働者災害補償保険法 2点以上 厚生年金保険法 2点以上 その他 3点以上 |
| 7.6% | 択一式 | 44点以上 | 各科目 4点以上 |
| 平成20年度 (第40回) | 選択式 | 25点以上 | 健康保険法 1点以上 厚生年金保険法 2点以上 国民年金法 2点以上 その他 3点以上 |
| 7.5% | 択一式 | 48点以上 | 各科目 4点以上 |
| 平成19年度 (第39回) | 選択式 | 28点以上 | 各科目 3点以上 |
| 10.6% | 択一式 | 44点以上 | 各科目 4点以上 |
| 平成18年度 (第38回) | 選択式 | 22点以上 | 労働基準法及び労働安全衛生法 2点以上 労働者災害補償保険法 2点以上 雇用保険法 2点以上 社会保険に関する一般常識 2点以上 厚生年金保険法 2点以上 その他 3点以上 |
| 8.5% | 択一式 | 41点以上 | 労働基準法及び労働安全衛生法 3点以上 労務管理その他の労働 及び社会保険に関する一般常識 3点以上 その他 4点以上 |
平成18年度から令和3年度までのデータでは、
選択式試験の合格基準は総得点は21点~28点以上、科目の最低点は1点~3点以上である。また択一式試験の合格基準は総得点は41点~48点以上、科目の最低点は3点~4点以上である。
このデータから合格基準は毎年大きく変動しているが、合格基準が下がれば合格率が上がるというような単純なものではないこともわかる。
社労士試験の合格基準の考え方について
厚生労働省から”社会保険労務士試験の合格基準の考え方について”が発表されている。合格基準の考え方は下記の通りである。
参考1
社会保険労務士試験の合格基準の考え方について
1 合格基準点
合格基準については、国民に分かりやすい簡易なものとすることが望ましいことから、平成12年度より、出題形式(選択式40問、択一式70問)、過去の合格基準の動向及び他の試験制度の現状を考慮し、次の条件を合格基準点とした。
選択式試験 総得点 40点中 28点以上(12年度平均点 25.9点) ※満点の7割以上
各科目 5点中 3点以上 択一式試験 総得点 70点中 49点以上(12年度平均点 35.1点) ※満点の7割以上
各科目 10点中 4点以上 2 年度毎の補正
上記合格基準点については、各年度毎の試験問題に難易度の差が生じることから、試験の水準を一定に保つため、各年度において、総得点及び各科目の平均点及び得点分布等の試験結果を総合的に勘案して補正を行うものとする。
(1) 総得点の補正
①選択式試験、択一式試験それぞれの総得点について、前年度の平均点との差を少数第1位まで算出し、それを四捨五入し換算した点数に応じて前年度の合格基準点を上げ下げする(例えば、差が△1.4点なら1点下げ、+1.6点なら2点上げる。)。
※ 前年の平均点との差により合格基準点の上下を行うが、前年に下記③の補正があった場合は、③の補正が行われなかった直近の年度の平均点も考慮する。
②上記①の補正により、合格基準点を上下させた際、四捨五入によって切り捨て又は繰り入れされた小数点第1位以下の端数については、平成13年度以降、累計し、±1点以上となった場合は、合格基準点に反映させる。ただし、これにより例年の合格率(平成12年度以後の平均合格率)との乖離が反映前よりも大きくなった場合は、この限りではない。
③下記(2)の各科目の最低点引き下げを2科目以上行ったことにより、例年の合格率と比べ高くなるとき(概ね10%を目安)は、試験の水準維持を考慮し合格基準点を1点足し上げる。
(2) 科目最低点の補正
各科目の合格基準点(選択式3点、択一式4点)以上の受験者の占める割合が5割に満たない場合は、合格基準点を引き下げ補正する。
ただし、次の場合は、試験の水準維持を考慮し、原則として引き下げを行わないこととする。
ⅰ) 引き下げ補正した合格基準点以上の受験者の占める割合が7割以上の場合
ⅱ) 引き下げ補正した合格基準点が、選択式で0点、択一式で2点以下となる場合
出典:[参考1] 社会保険労務士試験の合格基準の考え方について(PDF:57KB)(厚生労働省)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/sankou1.pdf)を加工して作成
このことから、次の2つのことがわかる。
選択式試験問題にも十分時間をかけて勉強する
科目の最低点の合格基準は、択一式試験は全科目とも10点満点中4点以上あれば突破できるので一つの科目に対して6問まで間違っても合格の可能性は残っているが、選択式試験は5点中3点以上必要な科目があるので、3問間違えると合格が厳しくなる。
択一式問題は70点満点で試験時間が210分に対して、選択式問題は40点満点で試験時間が80分である。よって択一式問題の対策を重点的に勉強しがちである。
しかし、合格を目指すのなら
苦手科目を重点的に勉強することが必要
選択式試験、択一式試験それぞれの総得点は、前年より平均点が上がれば合格基準点も上がるので、簡単な問題は正解する必要がある。もし簡単な問題を間違えると、最低点の合格基準も満足できなくなる可能性が高い。
社労士試験合格のための勉強法
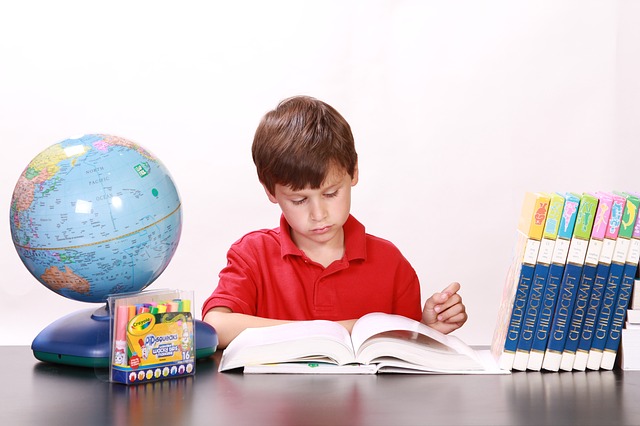
社労士試験は、勉強経験や受験経験があれば有利とは限らないのだ。
なぜなら社会保険労務士の試験科目である法律は、毎年法改正が行われていてその箇所は試験問題で出題される可能性も高い。よって前回覚えた知識がアダとなって、なかなか法改正の部分が頭に入らないのだ。これは社労士試験の宿命かもしれないが・・・
合格率が低いので1回の受験での合格は難しいかもしれないが、数回の受験で合格を決めてしまうのが良い。僕は数えきれないぐらい落ちたので言える立場でないが・・・
社労士試験合格には、それなりの勉強のコツがあるのだ。この勉強法を述べたいと思う。
基本書は何回も読む
社労士試験は科目数が多く、また関連する法律は更に多い。よって基本となる参考書(基本書)をじっくり読んでいると、最後まで読み終わるまでに相当の期間が経過していることになる。そうなると、最初の科目のことをすっかり忘れているのだ。また専門用語が多く、じっくり読んでも1回では理解できないことが多い。
わからないことがあっても、気にせずどんどん読み進めていく。なぜならわからない部分をじっくり読んでもほとんど理解できないからだ。むしろサッサと1回読み終わってから、再度読み直すと理解できることが多いのだ。
僕は社労士試験は基本書をじっくり1回読むより、回数勝負で何回も読む方が理解が進むので良いと思う。
また初心者の人は基本書を読む前に入門書を一通り読んで、頭の中に各社労士科目の引き出しを作っておくのも有効だと思う。
過去問重視で勉強する
過去問は絶対にした方が良い。過去問はあくまでも過去の問題で、同じ問題が出題される訳でないので無駄という人がいるが、僕は間違いだと思う。
試験は基本的に重要なところが出題される。過去に問題が出尽くしたからといって、重要でない問題が出たことはない。過去問で学習すれば同じ設問は出なくても、類似問題、良く出題される分野がわかるのだ。その後基本書を読み直せば、メリハリをつけながら読めるので記憶として定着するのだ。
僕は基本書⇒過去問⇒基本書⇒過去問と繰り返し勉強したが、これは非常に有効だったと思う。僕は時間がなかったので、解くというより設問、解答の順に読んで理解するという参考書の感じで使用した。過去問は6、7回は試験日までに繰り返し解いた。基本書では記憶として残りにくいが、実際の問題を読むことで記憶として残った。
横断学習で記憶を確実にする
社労士試験では、科目間で同じ項目、同じようで違う項目がある。例えば、国民年金法と厚生年金保険法だったり、厚生年金保険法と健康保険法だったり、健康保険法と労働者災害補償保険法だったりする。
勉強を進めるうちに、知らず知らずに間違えて覚えていることもある。
よって横断学習という違う方向から勉強することで、頭の中を整理でき、また他の科目も同時に勉強できるので一石二鳥である。
横断学習の参考書が出版されているので基本書の補助として、頭の整理に使用するのが良いと思う。
選択式試験対策が必要
社労士試験では択一式の問題数の方が多いので、選択式問題の勉強がおろそかになりがちである。しかし先ほど述べたように、選択式問題が意外と合否に分かれ目になることがある。よって、参考書を1回読み終わったら、隙間時間を利用して選択式の問題集に目を通すのが良いと思う。
苦手科目を得意科目にする
社労士試験は、科目の最低点は必ずクリアしなければ合格できない。また総得点も基準点以上をクリアしなければならない。そう考えると苦手な科目の点数を伸ばすのが合格の近道になる。
何回か基本書、過去問に目を通していくと、自分の苦手な科目がわかってくる。わかればそこを集中的に勉強するのだ。その科目だけなので日数はそんなにかからないと思う。そうやって苦手な科目を集中的じっくり勉強すると、その科目が得意科目になると思う。
苦手科目が得意科目に変われば、次に苦手な科目を探してこれも集中的に勉強して得意科目にしていくのである。
法改正、統計、白書対策は5月ごろから勉強する
過去問で勉強することが重要と書いたばっかりだが、過去問だけでは対応できない問題も試験では出題される。試験問題の解答で適用する法令等は試験年の4月中旬施行(受験案内に記載される)までである。
よって法改正で重要な箇所でありながら、まだ試験に出題されていない項目があるからだ。これだけは今まで試験で出題されていないので過去問の勉強では対応できない。
また労務管理その他の労働に関する一般常識や社会保険に関する一般常識の分野では、厚生労働省が毎年発行する「労働経済」、「厚生労働白書」、「労働経済白書」から出題されるのだ。
よって、法改正、統計、白書対策本を使用しての勉強が必要だ。大抵4月中旬以降、各社から発売される。また法令改正織り込み済みの模試(予想問題集)もこの頃から発売される。
過去問だけではカバーできない問題は、このような対策本、模試で勉強することが大切だ。
社労士試験を勉強するにあたって
社労士試験は合格率が近年5%程度であり、なかなか合格するのが難しい。また試験では各科目の最低点の基準をクリアしなければ合格できないため、実力があっても必ずしも合格できるとは限らない試験だ。
しかし、まぐれで合格できるほど甘い試験でもない。
合格した時の喜びはいいようがない。
受けるからには、ぜひ合格証を勝ち取って下さい。
健闘を祈ります。

